中学受験で中高一貫校に入学した私は、学業成績は低空飛行ながらも、音楽仲間のおかげでどうにか学校に通っていました。
私が通っていた学校はいわゆるエスカレーター式で、原則として高校入試なしに内部進学できるので、中学生時代は正直「どうせ受験勉強は必要ないしなあ」という安心感からなかなか勉強に本腰が入りませんでした。
ところが高校生になると、当然そうも言っていられなくなりました。
文理選択と目指す学部の決定
この学校は中学までは1学年3クラスですが、高校からは2クラス増えて、1学年5クラスになります。
受験勉強の末に高倍率の高校入試に合格した生徒が、2クラスぶん新たに入学してくるのです。
当然、私の校内偏差値は中学時代よりさらにガクッと下がりました。
これにはさすがに危機感を抱きましたし、大学受験のことも考え始めなければなりません。
そこでこのとき、私は苦手な理数系科目を捨てて文系での進学を目指すことにしました。
私は当時、好きな洋楽の歌詞をひたすら和訳していたせいか、英単語はそれなりに覚えられており、加えて高校1年の担任だった英語教師のロジカルな教え方がうまくハマったのか、英語の成績が急激に伸びていました。
すると、なぜか連動して国語でも文章の読解力が上昇し、文系の主要科目では好成績を維持できるようになりました。
私の認知特性によるものなのか、英文の仕組みを論理的に理解したとたんいきなり成績が上がり、自分でもびっくりしたことを覚えています。
そして、小さい頃から正義感というか倫理意識が強かった私は、「法律で人を助ける仕事がしたい」と考えるようになっていました。
結果、得意科目に加え、経済的な面も考慮して、進路については「国公立大学の法学部を目指す」という方向で固まりました。
進学先選びは正しかったのか?
「文系理系を得意科目で決める」というのは多くの高校生がやっていることです。
しかし、私の場合は自分の進路選択が正しかったのか、未だに考えることがあります。
というのも、発達障害傾向がある人って大体適正診断のようなものを受けると必ず「研究職向き」というような結果が出るんですよね。
志望校のレベルを落としてでも理系進学していれば、何か違う道があったかもしれません。
あるいは、進学校だけあってそんな生徒は少なかったですが、「専門学校で手に職」という選択肢もあったのでしょう。
ですが、当時は「自分は発達のいびつさ故に得意不得意の差が激しいのだ」などとは考えもしなかったので、得意科目とぼんやりした夢だけで進路を決めてしまったのです。
人間性を身につける練習
さて、話は変わりますが、高校生当時の私は俗に言う「人間観察」にはまっていました。
人付き合いが悪く、友人の少なかった私ですが、「クラスの人気者」にはやはり憧れがありました。
そこで私は、話しかけたときの反応、先生に叱られたときの応対、先輩・後輩それぞれに対する態度等、「人気者はなぜ人気者なのか」「どのような行動パターンが最適解なのか」を徹底的に観察していました。
その分析結果を実践するようにしていると、私に対する先入観を持っていない後輩はなんと私のことを社交的な人物だと勘違いするようになったのです。
結果として私は、同級生よりも後輩に友人が多いという、傍から見るとかなり不思議な状況になりました。
今思えば、ここで私は(凄く嫌いな表現ですが)いわゆる「健常者に擬態する」という能力を身につけたのかもしれません。

こうして徐々に人との付き合い方を学習していった私は、大学受験も無事突破し、近畿地方のとある大学の法学部に現役合格します。
初めての一人暮らし、そして自分がやりたい勉強ができるという期待感。
しかし、新生活への希望に心を躍らせる私を待っていたのは地獄でした。
続きはこちら↓

【私の小さい頃~大学生までの時期について書いた他の記事はこちらから】
→カテゴリー:私の幼少期~学生時代の話
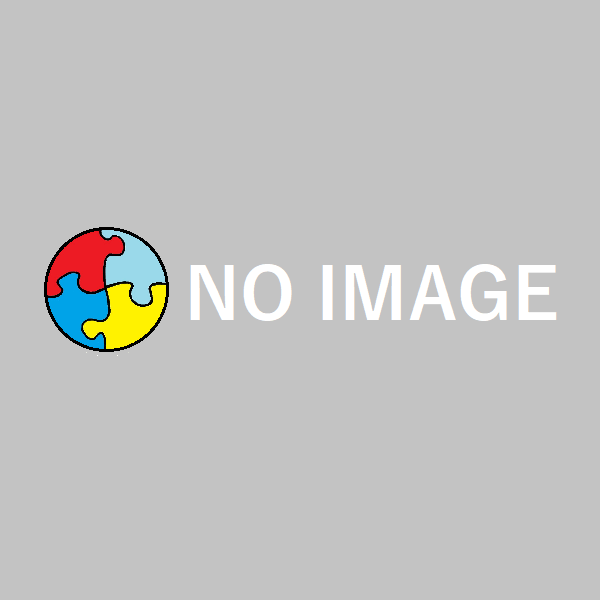
コメント