広汎性発達障害 境界域(グレーゾーン)の長男が通う幼稚園の運動会がありました。
このブログを書き始めてからは2回目の運動会になります。
幼稚園の先生方からいただく配慮を強く感じつつも、年長になった長男の成長を大きく実感できた運動会でした。
発達障害児にできる種目・できない種目
昨年の運動会については1年前に書きましたが、かけっこで逆走するというハプニング以外は大きなトラブルはありませんでした。

しかし今回は、去年とは異なり準備段階から先生方と連絡を取り合いながらの取り組みとなりました。
というのも、長男が通っている幼稚園は発表内容のレベルが高く、年長クラスにもなると、長男が参加するには厳しい部分が多いことが予想されたためです。
もちろん、障害の有無にかかわらず、子供の発達度合いによって完成度には個人間のばらつきが大きくあります。
しかしそれを加味しても、長男の今回の運動会で懸念される点はいくつかありました。
年長クラスの参加種目は、親子競技の二人三脚、団体競技のクラス対抗リレー、年長児全員参加のマーチングと、組立体操の4つです。
このうち、特に問題がありそうだったのがリレーです。
「前の走者がバトンを持ってくるのをスタート位置で待つ」、「他の走者がスタートするタイミングとは関係なく自分がバトンを受け取ったら走り始める」、「コースを走って一周する」、「もしバトンを落としたら拾う」、そして「次の走者にバトンを渡す」という重層的な競技は、彼にとってかなり理解が難しい様子でした。
子供のことを考えたときにどうすべきか
ここで親の立場としては、「無理を承知で参加させてもらう」というのも一つの考えとしてありだと思います。
しかし、それが原因で1位だったリレーがビリになり、長男がクラス中から総スカンを食らうという状況は避けたいところですし、本人の自己肯定感にも悪く作用しそうです。
そこでリレーに関しては、長男自身が意欲を示していなかったこともあり、「よーいドン!」の旗の係 兼 ゴールテープ係 ということで、競技自体には不参加ということになりました。
一方、親子競技の二人三脚については、自宅で練習を繰り返しました。
速く進みたいからといって、速いテンポで「1!2!1!2!」とやるのでは理解が追い付かないので、なるべく大股で「いーち、にーい、いーち、にーい、」と歩くという方策を取りました。
これはなかなか上手くいったと思います。
マーチングについては、本人が音楽好きということもあって、本番当日はうまく演奏できていました。
ただ、練習の初期は意欲がわかず、先生方に苦労をおかけしたようです。
というのも、長男は「音楽は好きだけど、子供が演奏する下手な音楽は嫌い」という性質なうえ、練習が始まったばかりの頃には全体像が見えないこともあってか、何をやったらいいのかが分からなかったのだろうと思います。
ともあれ、本番では最後まで演奏することができました。
(余談ですが、栗原類も「音楽は好きだけど音楽の授業は苦手だった」という趣旨の発言をしていましたね)

体操のクオリティで感じた成長
そして、長男の成長を一番感じることができたのが組立体操です。
音楽に合わせて、フラフープを使った演技やちょっとした組体操などを行うという種目です。
年長でもフラフープ回しができない子は多いですし、正直言って長男にそれができると思ってはいなかったのですが、彼はフラフープを持った状態で本人がクルクル回転するという方法で演技に参加していました。
それをやっていたのは長男だけで、全然フラフープを回せていない子は他に多くいましたので、先生からの発案だったのか、あるいはもしかすると本人が編み出したのかもしれません。
横に先生がついての参加ではありましたが、妻と二人で感動しながら見ていました。
ただ、反省点というか今後の課題も見えました。
長男は、事前に「今日は〇〇と〇〇をやるよ」と伝えたことには比較的しっかり取り組むことができます。
その反面、それ以外のことを適当にやってしまう節があります。
結果、競技についてのみ「頑張ろうね」と念押しをしたために、開会式の準備体操では突っ立っているだけ、そして閉会式では完全に「早く帰りたい」モードになってしまいました。
一日の予定を明確に全て伝えることの重要性を改めて感じました。
ともあれ、本人にとっては楽しい一日だったようです。
この調子で、工夫しつつできることが増えていったらいいな、と思います。
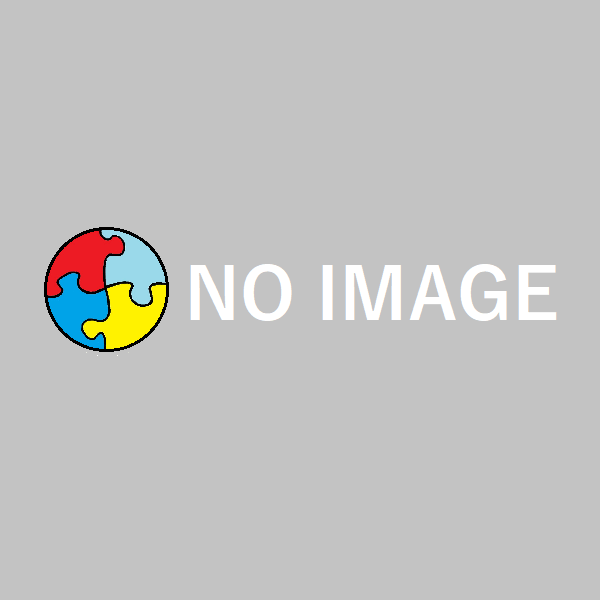


コメント