先日、2人の息子が通う幼稚園(認定子ども園)の運動会がありました。
発達障害グレーゾーンであり、今年で5歳になった年中の長男にとっては2回目の運動会です。
また、保育クラスに通う2歳の次男にとっては、初めての運動会でした。
発達障害と運動会
発達障害の子供を抱える親にとって、幼稚園の行事は不安が大きいものですが、実際のところ、子供たちの発達度合いはさまざまです。
発達障害のあるなしに関わらず、「お母さんと一緒にいたい」と泣く子もいるし、緊張して失敗してしまう子もいます。
年長さんでもそんな子はいますから、小さい子ならなおさらです。
以前に書いたとおり、2歳の次男は、今のところ特に発達上の問題は見受けられません。
幼稚園にもいつも元気に通っています。
そんな次男が参加する競技はひとつだけで、保護者と一緒のちょっとした障害物競走みたいなものだったのですが、いつもと違う雰囲気に耐えられず、大泣きしてしまいました。
そんな中にあって、長男はなかなか頑張っていました。
年中組の参加種目は、マーチング、保護者参加のデカパン競走(大きいパンツを2人ではいて走るやつ)、パラバルーン、そしてかけっこの4つです。
マーチングは、本人が音楽が好きということもあってか一生懸命太鼓を叩いていましたし、デカパン競走はお母さん(妻)と参加したので問題ありません。
パラバルーンのときも先生の横だったのでなんとかなっていましたし、先生が近くにいない時は近くの子に「違う!こっち!」と手を引っ張られながらも、本人は楽しそうにやっていました。
逆走ハプニング発生
ただ、かけっこで思わぬハプニングが発生しました。
年中組のかけっこは、4人が「よーいドン!」でいっせいに走るというもので、トラック1周の4分の3を走ったらゴールです。
ところが長男は、皆が同じ方向に走る中、スタートしてからしばらくするとふと立ち止まり、逆方向を向いてスタート地点に向かって走り始めたのです。
妻は「なんで!おーい!反対反対!」と言っていましたが、私はこの様子を見ながら「はあーそうか、その方がゴールに近いもんなあ」等と考えていました(長男がそう考えていたかは分かりませんが)。
結局、長男は逆走半ばで先生に捕まり、先生と手をつないでゴールまで走っていき、無事ゴールしました。
実は今年の運動会では、台風が接近していたため、予行演習が実施されていませんでした。
そのため、長男は「かけっこはスタートからゴールまで走る」という情報だけをインプットした状態で本番に臨んでしまったのかもしれません。
なんせ周りを見ることができない子なので、今後は「本人のストレスにならないよう配慮しながら周囲の状況を観察する練習をする」という必要があるな、と感じた一日でした。
結果オーライだと思ったこと
ただ、私個人としては、「ゴールテープを切る」という成功体験をさせてあげられたのは結果的に良かったと考えています。
普通にかけっこしていたら完全にビリだったので、おそらく先生が持っているゴールテープを切ることはできなかったでしょう。
失敗と思える出来事の中にも、その中で得られる経験はあります。
私は正直、父親としてそういうものを見過ごしがちなので、こういうちょっとした成功を見逃さないように気をつけたいと思いました。
【1年後、年長の運動会の話↓】

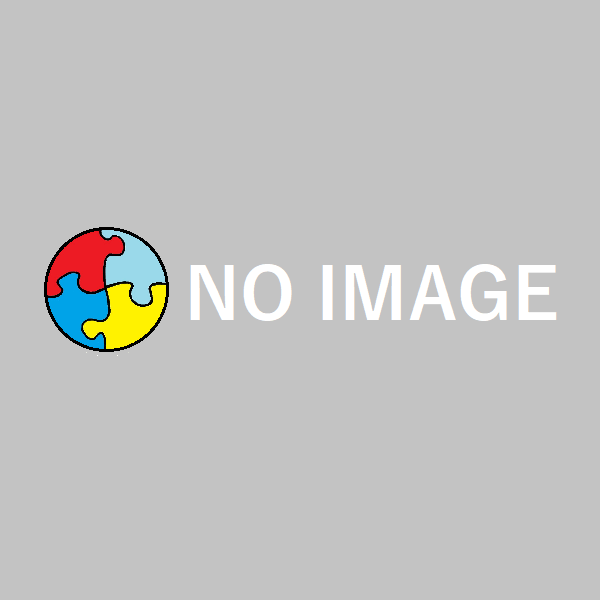
コメント