前回に引き続き、発達障害検査の結果の説明を受けた記録です。
※注意:検査を受けたときの記事では、検査の内容は大体の雰囲気が伝わる程度にしか書きませんでしたが、本記事では具体的な検査内容や、「どう答えてどのような結果が出たか」にも触れています。
これから検査を受ける方がこのブログをご覧になる場合、検査結果に影響する可能性もありますので、閲覧はご自身の責任でお願いします。
【発達障害検査に関する一連の記事はこちらから】→カテゴリー:私の発達障害検査の話
検査で分かったこと
検査の結果として、まず、私の知的能力は「特に高い」と判定されました。
ただ、得意不得意のばらつきが大きく、そのうえトライアンドエラーで自力で対処法を身につけている部分が多いことから、実際には数値以上に得意不得意の差は激しいかもしれない、と指摘されました。
少し前にSPIの勉強をしていたのも影響したかもしれません。
また、「明示されていない事柄を理解するのが苦手」「重要ではない細かい部分に目が行きがち」という特性から、仕事等で時間を無駄にしないためには指示を受ける際にあらかじめ細かい条件を提示してもらうべきとのことでした。
そして、人物像の把握が苦手であること、思い込みによって状況の理解が難しいことがあるため、正しい状況を周りの人と一緒に確認するよう心がけるのがよいとも言われました
次に、情緒面においては、わずかな刺激によって大きく動揺すると指摘されました。
また、物事に柔軟に対応することが苦手で、不適切な認知や判断によって誤った行動を起こしやすいために、会社員生活における対人関係で、耐性を上回るストレスを常に受けているような状態だったのではないかと言われました。
診断はつかなかった
ですが、これらの検査結果を総合的に判断した結果、私には何の診断もつきませんでした。
知能検査の結果を見ると凸凹があり、得意不得意の差が激しいことは事実だが、苦手なものでも平均値は超えており、IQも高い。
ASD(自閉症スペクトラム障害)の傾向が強く、社会生活を送る上での困り感は大きいと思われるものの、自分なりの対処法を編み出している部分も多い。
そのため、発達障害グレーゾーンとは言えるものの、今回の検査結果をもって特定の障害であると診断するには至らない、と。
正直、個人的には一番避けたかった結論でした。
なんせ、この時点で私は既に会社を辞めており、仮に再就職するとしても大卒の30代に求められるレベルで仕事をこなすことはどう考えても不可能な状態になっていたからです。
「もし発達障害の診断が出れば、精神障害手帳を取得できるかもしれない。そうなれば障害者雇用専門の転職支援サービス等を利用できるし、障害者として無理のない範囲で働けるかもしれない」というのが私に残された希望でした。
ですが、この診断をもって私には「会社員として組織の中で働くのは大変だろうけど、あなたは障害者ではないよ」という現実が突きつけられたのでした。
専門医による検査で診断がつかなかったのだから仕方ありません。
が、「正社員としてまともに働くことはできないけど、社会保障の助けも得られない」という、ある意味一番困ったことになってしまった私は、途方に暮れるしかありませんでした。
【追記】思いがけず続き。再度検査を受けることを決心しました。↓

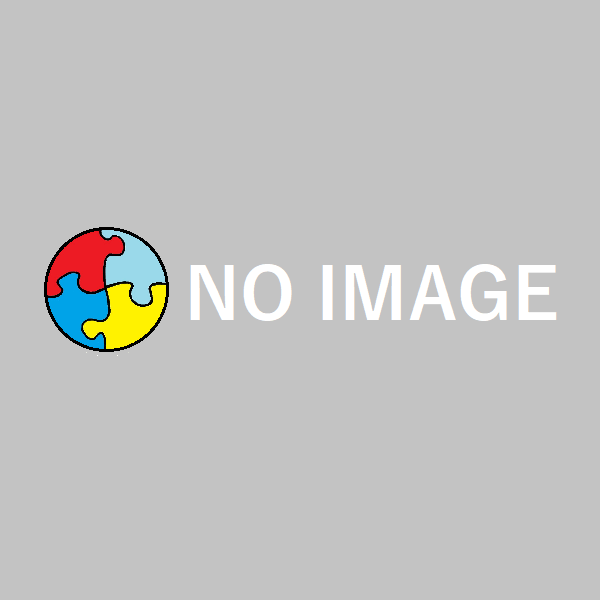
コメント