近所の公立小学校に通っていた私は、多少の対人トラブルを起こしつつも、不登校になったりすることはありませんでした。
しかし、小学生も4年生ぐらいになると、クラス内で色々な対立が起こるようになり、クラス内の序列、いわゆるスクールカーストも明確になってきます。
「発達障害」など全く認知されていない当時において、一方的にバーッと早口で喋ってしまう癖がなかなか直らず、人付き合いも相変わらず苦手だった私は、見事にスクールカーストの下層部分に位置することになってしまいました。
いじめとその原因(らしきもの)
幸いにも学業成績が良く、担任教師から目をかけられていたためか、表立った激しいいじめは受けませんでしたが、無視されたり、持ち物にいたずらされたりということが時々起こるようになります。
しかし、友人が少ない私はどうしたらいいのか分からず、休み時間のたびにその場にいるのが耐えられなくなり、トイレに逃げ込む日々が続きました。
ストレスから自分の髪の毛をブチブチと抜く癖がついてしまったのもこの頃です。
ただこれは当然の帰結というか、今思えば当時、周囲から浮くようなことを無自覚にやらかしていたのは間違いありません。
例えば、私は「目の前のA君と会話しているのに、隣で別の会話をしているB君とC君の話がA君の声と全く同じ音量で聞こえてしまい、A君を放置してB君とC君の会話に乱入してしまう」というようなことが多くありました。
また、そうでなくても興味のないことには集中力が全く続かないので、会話の途中なのに、読んでいた本の続きが気になってその場を立ち去ったりしていました。
妙なこだわりと自分を抑える努力
「どうでもいいことへのこだわりが抑えられない」というのは、高学年になっても治まることがありませんでした。
強く覚えているエピソードとして、(学校ではなく家でのことですが)私が買ってもらった本を兄が先に読み始めたことに対し、泣き叫んで激怒したことがあります。
兄からは謝られましたし、両親からもなだめられましたが、私は「自分が想定していた完璧な状態」を崩された怒りが数日経っても収まらず、その本を1ページも読むことなく捨ててしまい、貯めていた小遣いで同じ本を買い直しました。
とはいえ、自分の行動を「これは直した方がいいのかな?」と客観的に考えられるようになってきたのもこの時期です。
頭の中では別のことを考えていても、一応は人の話を最後まで聞くということを心がけたり、兄や友人に手伝ってもらい、ゆっくり喋る練習をしたりもしました。
「逃げ」としての中学受験
それでも、一度ターゲットになったいじめは完全には収まらず、中学への進学で状況が改善するとも思えませんでした。
その上、自分が住んでいた地域はヤンキーが多く、進学予定の公立中学もかなり荒れていて、平穏な生活は望めないような状況でした。
そこで私は、電車で40分ぐらいのところにある、進学校として有名な国立大学付属の中高一貫校を受験しようと考えるようになりました。
安直な考えではありますが、当時の状況から抜け出すには良い方法だったと思います。
両親に頼んでみると、「いい学校と聞いているし、国立なら授業料も高くないし…」ということで、この要望はすんなり通りました。
そして、それまで以上に勉強に力を入れるようになった私は、中学受験を突破し、その中高一貫校に無事合格することができました。
このとき私は、落ち着いた環境で中学校生活を送れると思い、ほっとしていました。
同じ小学校からの進学者は私ともう1人しかいなかったため、「小学校では嫌なことばっかりだったけど、これで人生大逆転だ!」と、中学デビュー的なことを想像したりもしました。
ところが、残念ながら私は華やかな世界は自分に無縁のものだとすぐに思い知ることになります。
続きはこちら↓

【私の小さい頃~大学生までの時期について書いた他の記事はこちらから】
→カテゴリー:私の幼少期~学生時代の話
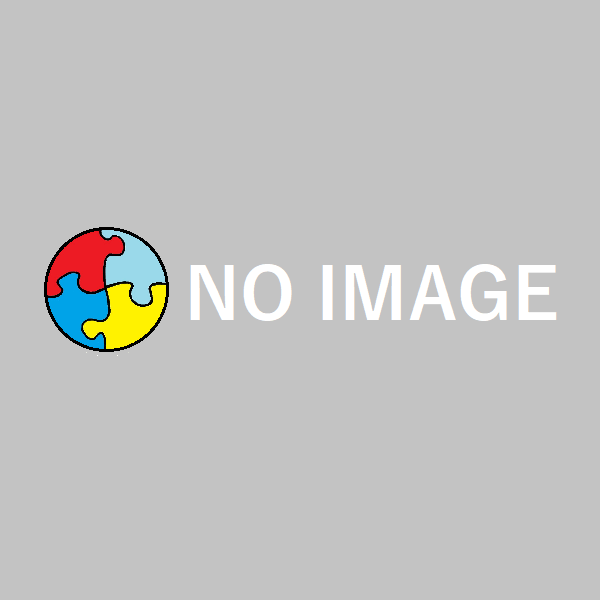
コメント